生理用品ブランド「ソフィ」を通して、女性がより自分らしく過ごせる社会を目指し、自分に合った生理ケアを行うことを推進する「#NoBagForMe PROJECT」。2019年に始動後、Twitterを中心に大きな話題となり、昨年にはPRアワードグランプリでシルバーを受賞した当プロジェクトは、メンバーのどのような想いのもとで生まれ、いかなる情報戦略によってこれだけの世論形成に成功したのでしょうか。
今回は、プロジェクト発起人であるユニ・チャーム フェミニンケアブランドマネジメント部ブランドマネージャーの長井千香子さん、博報堂ケトル ディレクターの村山佳奈女さん、博報堂 PRディレクター肥塚縫伊子さんの3名に話を伺いました。
CONTENTS
日本の生理用品マーケットの現状
性教育の遅れとユニ・チャームの創業背景

左から、ユニ・チャーム 長井さん、博報堂ケトル 村山さん、博報堂 肥塚さん
-はじめに長井さんのご経歴を教えてください。
長井:ユニ・チャームには、2004年に入社しました。翌年の2005年からマーケティング部門の配属になって以来、主に「ソフィ」を担当しています。これまでに2度産休を取得していて、復帰後はベビー事業なども担当しましたが、生理用品事業部に戻った後は、新事業として『はだおもい』ブランドの立ち上げや、パンティライナー『Kiyora』の育成などにも従事してきました。2019年には、タンポンの担当者と「#NoBagForMe PROJECT」を始動させ、メンバーの一員として参画しています。
-プロジェクトは何をきっかけに始まったのですか?
長井:ユニ・チャームは、日本国内で唯一タンポンを製造販売しているメーカーなのですが、日本のタンポン使用率は世界的に見ても非常に低いのが現状です。欧米では80%くらいの女性が利用しているにも関わらず、日本ではたったの25%程度。この結果からも、日本の女性にとって、生理用品の選択肢が非常に狭まってしまっていることがわかります。
タンポンは体内に入れる生理用品なので、生活者側からしても、CMで一方的に伝えられた程度では「使ってみよう」とはなかなかなりにくい商材です。使い始めるきっかけとして強い後押しとなっていたのは、“親しい人からのオススメ”でした。身近な母親や友人から勧められると、抵抗感が薄れつつ使い方の詳細がよく分かり、購買に繋がりやすいのです。しかし、そうした使用者が周囲にがいなければ、使う機会がないままになってしまいます。
一般的に生理用品は、初めての生理が訪れる12歳頃に母親から勧められたものを使い、大学生になる頃には生理に慣れ、20代前半頃までには自分で使用する生理用品が固定されてくる、という消費行動が見られます。そこで、20代前半頃までに「タンポン」という選択肢を知ってもらうためにも、クチコミをもっと増やさなければなりませんが、現時点で生理用品に関するクチコミ自体が非常に少ない。なぜなら、日本では生理がタブー視されているためです。
-タブー視問題に対する取り組みは、#NoBagForMe プロジェクト以前にも行っていらっしゃったのでしょうか。
長井:この問題に対するユニ・チャームの取り組みは、実は創業背景にも繋がってきます。創業された1961年は、日本では、生理用品がまだ薬局の奥に追いやられていて、“レジで店員さんに声をかけなければ買えない”というのが当たり前でした。そんな日本の薬局の現状を見た創業者が、アメリカに渡った際に店頭で堂々と並べられている生理用品を見て、「生理用品を日本でももっとオープンにしなければ」と強く感じたことがきっかけで、ユニ・チャームの事業が始まったんです。そのため、今回の取り組みも元を辿れば創業理念に通じてきます。
その後、創業者が生理用品の商流を作ったことで、ドラッグストアで棚に並べる権利を獲得。1970年代からはテレビCMの放送を開始し、様々なクレームと闘いながらも、市民権を得ることに成功しました。しかし、その後現在に至るまで大きなうねりは生まれず、数十年の間沈黙が続きました。
肥塚:この沈黙の間に「女性の社会進出」が広く普及しましたが、ここでも避けて通れないのが、女性の身体の問題です。職場の人に生理について話すことは勇気がいりますし、いざ伝えたとしても、なかなか理解されにくい部分があります。そのため、男性と同じように働くには、生理の辛さを隠し通さなければならないのが、これまでの女性の働き方でした。だからこそ次に取り組まなければならないのが、生理用品の選択肢を広げて日本の女性のQOLを高めることと、世の中全体のイメージを解きほぐして、生理について気兼ねなく話せる社会を実現することです。
村山:これまでユニ・チャームさんが取り組んでこられたことのインパクトって、非常に大きい。最近では「ブランドパーパス」などと言われることも多くなりましたが、そのずっと前から、例えば長井さんが「生理について気兼ねなく話せる社会にしたい」と語ってきたように、「ソフィ」には熱い想いを持った社員の方々が集まっている。生理のタブー視問題に対して真摯に向き合い続けているブランドなんです。
生理用品について会話されにくい世の中の空気

-先ほど、「20代前半までに生理用品の選択肢を広げてもらう必要がある」とおっしゃっていましたが、これについてはどのようにステークホルダーを設定されましたか?
長井:まず、日本で生理についての教育が遅れているのは紛れもない事実です。学校によっては、性教育に積極的なところもありますが、親御さんからクレームが来るなど、教育現場での普及ハードルはまだまだ高くなっています。そのため、生理用品の選択肢が広がるか否かは、“母親と娘”というクローズドな関係に大きく依存してしまっているのが現状です。
そこで、我々が捉えたかったひとつめのステークホルダーは、“友人同士”です。現在は4人に1人がタンポンを利用していますが、調査結果などからも、使用のきっかけは20代前半頃までに「友人と旅行や遊びに行く時に使い方を知った」という方が多いことがわかっています。しかし、ここで課題となるのが、親しい友人とメイクやご飯の話をするのと同じように、“生理の話”が入ってこないということです。そのため、「生理のことで悩んでいたら話していいんだよ」という空気感を、内と外から作りたいという想いがありました。
次に、このような背景を踏まえて、生理の話題を入れ込みやすいところはどこだろう? と考えた際に、もうひとつ上がったのが「企業」でした。これには、女性の部下を持つ上司への教育と、子を持つ親世代への再教育という、両方の意図が込められています。
肥塚:特に親世代の場合、保健体育の中でも「生理についての授業は女子しか受けていない」ということが多く、男性は学校で生理の教育をまともに受けられていません。また最近では、性犯罪も後を絶たない中で、「自らがきちんと性教育をしなければならない」と危機感を抱いている親御さんも増えています。そこで、教育現場よりも入り込みやすく、親世代へのアプローチが可能なコミュニティとして、企業をターゲットにしました。
「#NoBagForMe」で社会課題に立ち向かう
社会の利と会社の利を結ぶ「#NoBagForMe」

-このようなステークホルダー設定のもとで、実際に #NoBagForMe プロジェクトで取り組まれた活動内容を教えてください。
長井:取り組みの内容は大きく2段階に分かれています。第1弾の2019年6月からは、生理用品に関するクチコミを増やす土壌づくりのために、5名のKOLに参加いただき、SNSを中心に「生理に関する発話を促す」ようなコミュニケーションに挑戦しました。第2弾となる2020年からは、社会に対して性教育を行うために、企業向けの「みんなの生理研修」を開始しました。
-この社会活動的な取り組みに対して、目標はどのように設定されていたのですか?
長井:一つ目の目標は、長期的な視点で見て、「気兼ねなく生理のことを話せる社会の実現」です。その成果指標として、年代別のアンケート調査を定点的に実施し、世の中の「生理」に対する温度感を計ってきました。1000人以上の老若男女に対して、年代別のアンケート調査を実施しているのですが、それらの結果を見ていると、生理の当事者である女性でさえも、まだまだ正しい知識を身に付けられていないことが数字上でわかってきます。
二つ目は、プロジェクトを通じて「ナプキン以外の生理ケア用品の認知と使用率をあげること」です。これまでナプキンしか使用したことがなかった方に、タンポンなどの生理ケアに対して興味を持ってもらうことができれば、それが使用率の増加に影響し、我々の利にも直結します。そのため成果指標としては、ナプキン以外の生理ケア用品の使用率をトラッキングしています。
肥塚:現在日本でタンポンを製造しているのは『ソフィ』さんのみなので、ナプキン以外の生理ケア用品について知ってもらうことは、同時に「ソフィ=生理に様々な選択肢を提示しているブランド」と知ってもらうことにも繋がります。このような活動を年々継続して、ナプキン以外の生理用品の認知率と利用率を上げることは、女性のQOL向上に繋がるだけでなく、ソフィブランドの売上にも繋がるため、社会の利と会社の利が一致するんです。
「生理」を含むツイート数で前年比2倍を実現した情報戦略

-SNSを中心とした空気づくりについて詳しくお聞きしたいのですが、2019年に5名のKOLを起用されてから、具体的にはどのように情報を広めていかれたのですか?
村山:依頼する際に意識したのは、まずはコンセプトに共感してもらえることと、それぞれの特性がちがうこと。その上で、これまで「女性の地位向上」や「ジェンダー問題」などについて発信し続けてきた方々を「生理を語る理由のある人」として位置付け、KOLとして参画してもらいました。また、別々の分野で活躍している面々に依頼することで、より多く、様々なフォロワーへのリーチを試みました。
オファーの仕方についても、基本的には「こういうプロジェクトに取り組もうとしているのですが、どう思いますか?」という相談の形を取りました。その結果、お願いをした5名のみなさん全員から快くOKをいただくことができました。
-アサインの時点で熱量の高いKOLを集めることができたんですね。
村山:5名のみなさんには、プロジェクトメンバーの一員として、いわゆる従来の「インフルエンサー施策」とは一線を画すような活動を行っていただきました。例えば、月に一度のミーティングを開催し、 生理のタブーを解決するためのディスカッション、講義に参加してもらうなど。これまで接点のなかった面々が、ミーティングに出て語る場を作ったことで、この取り組みを“広告のフィクション”ではなく、“ドキュメンタリー”として世の中に出すことができました。
肥塚:また、いわゆるインフルエンサーの投稿のように、企業が指示した内容をそのままSNSに書いてもらうのではなく、KOL自身の声で書いてもらうことで、ファンの方に関心を持ってもらいやすい状態を作りました。KOLが発信する内容については、実は一度もこちらで確認を行っていません。生理について語る必然性がある面々が投稿しているため、フォロワーの方々にも違和感なく受け止めてもらえたのではないかと思います。
センシティブだからこそ“一般的な話題感”を醸成する

-「生理」に関する発話を促すという点では、日本の性教育の遅れだけでなく、「言わないことが美」とする日本人の価値観も、大きなハードルとしてあったのではないかと思います。そこの壁を超えるために、何か意識されたことや工夫されたことはありますか?
長井:まさに、「生理」という触れにくい話題については、掴みどころを作る必要があるので、「何に変換して語るか」を大切にしていました。例えば、「女性の生理による経済損失額は約6000億円」などと言うと、男性も興味を持ちやすくなります。これらの成果や変化を測るためにも、2019年からは、男性も定点調査の対象に加えました。
村山:また、5名のKOLに加えて、芸能人や婦人科医の方々、男女10名を含めたコミュニケーション活動も行いました。この10名をアサインすることによって、生理を“一般的な話題”として演出し、世の中にプレゼンテーションすることを意識したんです。何においても、テレビで取り上げられることによって、その話題が市民権を得た感じがしますよね。2020年には、私たちも企画スタッフとして関わった『生理キャンプ』という特番がテレビ東京で放送され、大きな反響を得ました。
肥塚:プロジェクトが始まった頃は、チーム内ですら生理を“隠語”で話していましたが、今では全くそんなことはしなくなりましたね。やはり、生理の話題に触れる機会を増やすことが大事なんだなと思います。
長井:加えて、婦人科医の方をプロジェクトメンバーとしてアサインしていたことも、ポイントのひとつです。“我慢が美徳”という日本特有の価値観も影響し、「生理痛くらい我慢しないと」と思ってしまう女性が多いようです。そのため、婦人科に通う女性の数は世界的に見て少なく、妊娠してから子宮筋腫が見つかるようなことも多々あると、婦人科医の先生方から知らされました。だからこそ、「我慢しなくて良いんだよ」ということを婦人科医の先生から言っていただくことで、婦人科に通うハードルを下げ、同時に生理についても会話しやすい空気が作る。そのため、婦人科医の方を積極的にプロジェクトに巻き込みました。
「#NoBagForMe」で変化した世の中の課題感
企業向けの生理研修が福利厚生を見直すきっかけに

企業で実施された『みんなの生理研修』
-#NoBagForMe プロジェクト開始から、どのような反響や成果が得られましたか?
長井:プロジェクト開始後、Twitter上の「生理」に関するツイート数は前年の2倍にまで増加しました。生理について話す人や、話すきっかけを増やすことができたのは、成果として非常に大きかったと思います。しかし、ソーシャルイシューの調査を実施して、具体的に生理の何について話されていたのかを調べると、“社会の中での生理”や“対人関係”に悩みを抱えている女性が非常に多いことがわかりました。生理にまつわるフラストレーションを解決するために、その後の企業の生理研修へと繋がっていきました。
-企業研修のあと、何か企業側で新たなアクションは生まれましたか?
長井:研修後に「生理休暇」の制度内容を見直した企業や、会社の福利厚生として、トイレにサニタリーを設置するような企業がありました。
村山:「生理の貧困」はじめ、世の中にはまだまだ表面化されていない課題がたくさん潜んでいることを思い知らされます。 政治家に女性が少ないことから、これまでどうしても生理に対する経済的な優先順位が低くなってしまい、大事な議論から抜け落ちてしまっていたんでしょうね。
肥塚:「女性の健康」や「生理」というテーマは、取り掛かるべきシーンが非常に多いです。今回も、取り組みのインパクトや社会へのメッセージ性という視点から、企業への研修を行うが良いのではないかと考え、「みんなの生理研修」実施へと踏み出しました。初めは、無料研修として公募制で行っていましたが、後半には企業側から「研修を行いたい」と声をかけていただける機会が増えたことも、大きな成果のひとつだと思います。
PRの力で巨大な社会課題に立ち向かう

-「#NoBagForMe」の活動を通じて新たに感じたことや、これから取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
肥塚:2019年はちょうど社会が変わり始めたタイミングだったため、世の中のテンションや動きをかなり意識していました。プロジェクトメンバーの間では、「2019年に始まっていなければ、遅すぎたね」という話もしました。
長井:生理の話が世の中でされるようになってから、生理にまつわる課題感も変わってきた気がします。当初は生理用品のパッケージデザインなどを取っ掛かりにしていましたが、今後は生理の貧困や性教育、また東京と地方の情報格差など、もっと根本的な課題にアプローチしていく必要があると感じています。SNS上の声を見ていても、生理のタブー視にまつわるコミュニケーション齟齬や、体調への不安を抱えている人の声が広がっているので。
-ローカルでいかに世論を作れるかは、今後の大きなテーマになりそうですね。
村山:近年、女性の課題をテクノロジーで解決する「フェムテック」が話題です。ただ、こうした言葉も、まだまだ全国規模では知られていないのが現状。最先端のデリケートケア商品を取り扱っているお店も、都市部にしかありませんから。日本中、生理のあるすべての人に、良質なソフィの商品を知ってもらい、届けることには大きな意味があると考えています。
肥塚:また、今後の日本の女性のQOLを上げていくという活動において、PRは非常に重要な役割を担っています。そこら中に転がっている根深い社会課題に対して、1社だけで立ち向かおうとすることはどうしても難しいです。だからこそ、今回の「#NoBagForMe」のように、様々なステークホルダーとリレーションを築き、巻き込んでいくことによって、成し得ていくものがあると思います。
長井:そうですね。生理のある女性にとって、生理は自分の生活に密接にかかわってくるものです。これからもこの活動を通じて、生理の心身のトラブル解決だけでなく、社会の中の生理タブー視によって、生理で困っている人が見過ごされないような社会を創れるよう、尽力していきたいと思います。
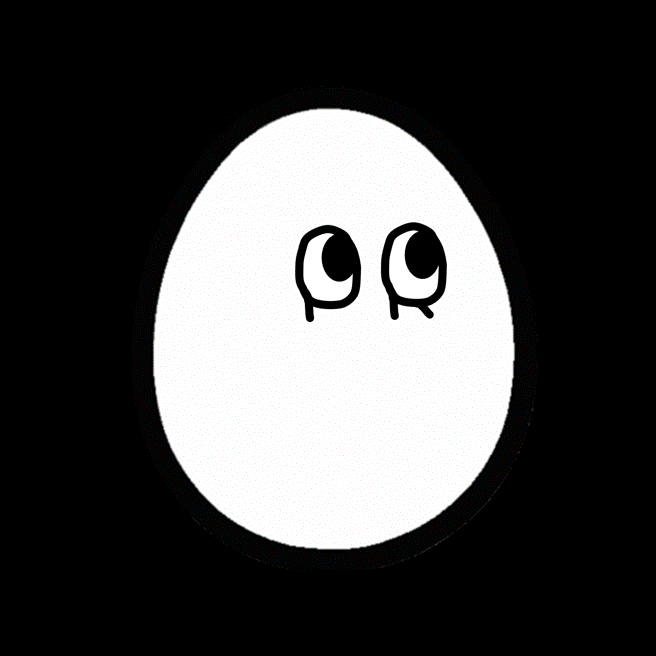
1995年生まれ大阪育ち。2018年同志社大学卒業後、株式会社マテリアルに新卒入社。1年目でウェブメディア『PR GENIC』を立ち上げ、記事の執筆と編集全般や、セミナーの企画など、コンテンツ作りを幅広く担当。半年間ハウスメーカーのマーケティング部への出向も経験。現在はオープンイノベーション支援に従事しつつ、外部アドバイザーとして編集のサポートを行っている。














