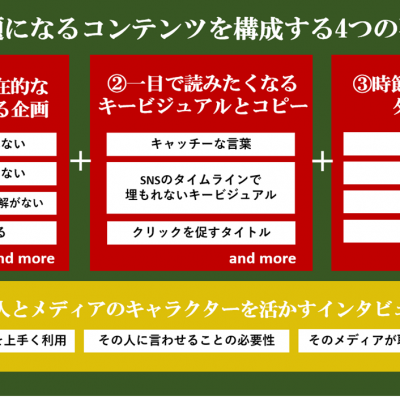ネットメディアや動画配信サービスの勢力が増し、生活者の“マスメディア離れ”が叫ばれている今、ある地方紙の取り組みが盛り上がりを見せています。それは、西日本新聞社の『あなたの特命取材班』です。LINEなどを活用して市民から寄せられた相談に応える報道スタイルで、多くの読者から支持を得ている『あなたの特命取材班』は、「かんぽ不正販売」報道の原点になるなど、社会にも大きな影響を与えています。
今回は、そんな『あなたの特命取材班』を生み出し、社会部遊軍キャップ、クロスメディア報道部シニアマネージャーを経て、2020年8月から中国総局長として北京に赴任した坂本信博さんに、「生活者に支持されるジャーナリズムの真髄」について話を伺いました。
CONTENTS
グローカルメディアの新たな可能性を探る西日本新聞
現在日本には、『読売新聞』『朝日新聞』などのように全国のニュースを幅広く報道する「全国紙」、それぞれの地域に根差しつつ広域的な視点でニュースを伝える「ブロック紙」、県内のニュースに注力する「県紙」など、さまざまな種類の新聞が100紙以上存在しています。
この中の「ブロック紙」のひとつである『西日本新聞』は、暮らしの疑問や地域の困り事、行政・企業の不正告発まで、読者の情報提供や要望に応えるオンデマンド調査報道『あなたの特命取材班』を、3年前にスタート。広域的な視点で地域に根ざした取材ができるという、ブロック紙ならではの強みを生かしたこの活動は、現在地域や媒体の垣根を超えて、日本全国に広がりつつあります。
調査報道『あなたの特命取材班』のはじまり

―『あなたの特命取材班』(以下「あな特」)を始めたきっかけを教えてください。
『あな特』を始めたきっかけは、“読者離れ”と“記者離れ”という、かつてないふたつの危機感からでした。“読者離れ”については、新聞の発行部数自体が大幅に減少していて、読者の高齢化も進んでいます。また、フェイクニュースが氾濫して「マスゴミ」という言葉が生まれたり、デジタルへの対応の遅れが目立ってしまったりと、さまざまな要因が絡んで深刻な読者離れを招いている現状です。
そして特に地方紙で深刻なのが、“記者離れ”です。「地方紙には将来がない」と感じて、有望な記者が相次いでNHKや全国紙に転職してしまう時期がありました。また、記者の負担軽減などで「お客様センター」という電話窓口ができたことによって、読者の生の声が直接編集局に届きにくくなり、世のため人のためになりたいと思って記者になった人間が大半の中で、読者からの手ごたえを感じにくくなったことも、記者離れのひとつの要因になっていると思います。
これらの問題を一挙に解決できる方法はないだろうか?そう考える中で生まれたのが、『あな特』です。我々のような地方紙にしかできない仕事が、必ずあるはず。読者のニーズを掴む仕事を作ろう。読者への信頼を高めてファンを増やそう。人の役に立てて、記者自らが書きたい記事を書ける仕組みを作ろう。そして、紙にもデジタルにも強いコンテンツを生み出し、記者が読者と繋がっている手ごたえを感じられる仕組みを作ろう。そう思って始めました。
『あなたの特命取材班』が持つ社会への影響力

―どのようにして読者と繋がる仕組みを生み出したのですか?
手法をご紹介すると、まず『あな特』のLINE公式や特設サイトから、暮らしの疑問や地域の困りごと、不正の告発などについて、読者から直接調査依頼が寄せられます。これらの依頼内容は、200名ほどの記者に一斉に届くようになっており、「これやりたい!」と最初に手を挙げた者が返信をして、取材や調査を行うという、“手挙げ方式”で担当者を決めています。そして紙とウェブの両方で記事化して、その中でも反響の大きいものがあれば、さらに取材調査を深めて記事化させていく仕組みです。
読者と直接繋がる手段として、LINEを使ったことが非常に大きいです。LINEは、従来“電話が担っていた役割”に非常に近いと感じています。読者起点の調査報道というものは、約150年前に日本に新聞が誕生したころからあり、決して目新しいものではないのですが、決定的な違いは“SNSを使って双方向のやり取りが可能になった”ことです。
また、このLINE公式を用いて読者から調査依頼が寄せられるだけでなく、取材自体に読者にも参加してもらったり、我々からアンケート協力や情報提供を呼び掛けたりすることもあります。このように、ひとりひとりの読者と繋がって、いつでも双方向のやりとりができるというのが、『あな特』の強みです。
―読者の”知りたい”に答えるジャーナリズムとして、LINEを用いた手法以外に、従来からアップデートされたものなどはありますか?
『あな特』のコンセプトとして、①SNSを活用した読者との双方向性、②取材の手法や過程の可視化、③新聞社の取材力を発揮して課題の解決を目指す、この3つを掲げているのですが、これらに基づいて「問題を深堀りして、時代性や社会性を描きながらグレーゾーンに切り込んでいく」ことを大切にしています。
また『あな特』の場合、投稿者の困りごとが、他の人にも共通しそうかどうかを判断基準に、調査対象を選定します。このような活動を通して、新聞の信頼性を高めてファンを増やすことが出来るのか、新聞ジャーナリズム生き残りへの実験的な意味も込めているんです。
例えば、あの「かんぽ生命保険の不正販売問題」は、『あな特』に寄せられた調査依頼がきっかけで報じたニュースでした。もともとのきっかけは、「暑中見舞いはがきの自腹営業に困っています」という現役の郵便局員の方からの調査依頼で、これを受けてかもめ~るに関する記事を出したところ、日本郵便が年賀状や暑中見舞いのはがきのノルマを廃止するに至りました。しかし、その後また別の郵便局員の方から、「実はもっとひどいノルマがある」と連絡が来たんです。その内容が、「かんぽ生命保険のノルマ」でした。それから担当記者が取材を積み重ねていく中で、不正販売が全国的に行われているということが分かり、日本郵政グループのトップ3名が辞任する事態になりました。
『あなたの特命取材班』を通じて社会参加する読者

―全国的に大きな問題になったニュースも、実は『あな特』の発祥だったんですね。
そうなんです。このほかにも、具体的に課題が解決されたという事例が相次いでいます。「高速バスに優先席がない」という相談を受けて報道したところ、実際に高速バスにも優先席が設置されたり、「隣人のベランダのたばこの煙で困っています」という福岡の主婦の悩みが、実は全国で起きている普遍的な社会問題だったことが、報道を通じて分かったり。
また、『あな特』の記事は、Yahoo!トピックス掲載率が非常に高いと感じています。Yahoo!トピックスに掲載された時のPV数は数百万〜1000万PVまで到達していて、新聞の発行部数が減少傾向にある中で、ウェブ記事がどんどん読まれるという現象が起きています。
―なぜYahoo!トピックスの掲載率がそれほど高いのでしょうか?
「グレーゾーンに切り込む」っていうのが、実はウケが良かったのかもしれません。悪事をスパっと一刀両断に弾劾するような記事もいいんですけど、すぐに結論は出ないけど悩ましい、ああでもない、こうでもないって議論したくなるような記事が、多くの方の共感を呼んだ面もあるようです。ひとりひとりの困りごとに徹底して寄り添った結果、それが地域内だけでなく、全国の方の支持を得ることにも繋がったのではないかと思います。
あと、これは初めから狙っていたことではないのですが、『あな特』の記事の書き方がウェブに向いていたんですよね。新聞は通常「逆三角形型」と言われる書き方で、タイトルや最初のリード文だけを読んで内容が理解できるように作られています。一方、ウェブの場合、クリックしてなるべく最後まで読んでもらわなければならないので、見出しだけ読んで内容がわかってしまってはいけない面があるんですよ。『あな特』の場合は、『探偵ナイトスクープ』のように、相談内容があって、それに対してこのような調査を行って、その結果こういうことが明らかになって…と、最後まで読まないと結論がわからない構造になっているので、結果的にクリックされて読まれるようになったのではないかと考えています。
―読者からは『あな特』に対してどのような反響がありましたか?
これまでに寄せられた調査依頼は14,000件で、記事の総本数は約500本、累計PV数は3.8億PVに到達、LINEの友達登録者数は17,000名になりました。このように、読者の方々の支持のおかげで順調に数字を伸ばしていますが、読者の方々は『あな特』を“社会とつながる窓”として捉えて下さっているようです。
今年1月に一度だけ、あな特通信員の方々に向けて「あなたはなぜ、あな特通信員でいてくれるのですか?」というアンケートを行ったんですけど、その結果最も多かった答えは「困ったことや悩み事が出来たときに相談したいから」でした。また、「あなたにとって『あな特』とは何ですか?」という質問に対しては、「社会参加」という回答が最も多い結果に。この結果を見て、『あな特』が一種の社会インフラになりつつあることを実感しました。
地域市民や若者を巻き込むジャーナリズム
「相談先がない」情報社会における生活者の実態

―多くの人が『あな特』について“社会参加”と回答されていたとのことですが、地域単位で何かに取り組む際の市民の巻き込み方や、地域世論の作り方について、坂本さんはどのようにお考えですか?
「世の中をよりよくしたい」と思っている市民の方はたくさんいらっしゃるので、そういった方々と繋がっていくことが大切だと思います。これおかしいなと思ったり、もっと暮らしを良くしたい、改善したいと思ったりしても、相談する先がなくてどうしたらいいかわからない。そう困っている方が、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方々が、どんなことに困っていて、どう変わってほしいと思っているのかを吸い上げることは、今の行政や企業にはなかなか出来ていない部分だと思います。なので、そこで我々新聞社が“よろず相談窓口”みたいな感じで、社会インフラとして機能していくことができれば、新聞社はまだまだ生き残れるんじゃないかなと思っています。
―「世の中をもっと良くしたい」と思っている地域市民は多いけど、どこにその思いをぶつければいいのかがわからないという状況なんですね。
まさにそうなんです。『あな特』をやってみて思ったのは、現代は「情報社会」と言われていますけど、実際はどこにも相談できずに困っている人が本当に多いということ。そして、新聞社が思った以上に頼られているということでした。様々な行政の窓口はありますけど、そこには手を伸ばせていない人が少なくない。かといって、自分の困りごとをどこに相談したら良いかもわからない。SNSを使って、誰でも簡単に情報発信できる社会になったとは言え、そこに発信されているのは氷山の一角でしかなかったんです。
また、些細な問題として見過ごされていることが、実は大きな問題だったりもします。しかし、寄せられた相談内容に対して、自分たちだけで解決することは到底無理なので。企業や行政、そして読者の方々と上手く連携しながら、世の中を良い方向に変えていくことが出来れば、多くの方に希望を持ってもらえるんじゃないかと思っています。
それに『あな特』は、実は我々にとっても“社会と繋がる窓”になっているんです。世の中でこんなことが起きているんだということを、読者から『あな特』を通じて教えてもらうことも結構多いんです。ですからこれからも、読者と記者のお互いにとっての“社会の窓”になっていけたらと思います。
SNSはマスメディア離れする若者との架け橋

―読者が高齢化していることに危機感を抱いていらっしゃるとのことですが、若い世代がメディアに求めているものって何だと思いますか?
今まで、若者がどのようなことを知りたがっているのかを聞く術もなかったんですけど、新たにLINEという窓口を設けたことで、中高生や大学生からの相談がたくさん寄せられるようになりました。例えば、新型コロナウイルス禍で一時期話題になった「9月入学案」についても、当時高校生から結構な数の相談がありました。特に受験生にとっては深刻な問題なので、この自分たちの声を世の中に届けてほしいと。
他にも、中学2年生の女子生徒からこんな調査依頼がきたことがありました。一昨年の非常に暑かった夏、炎天下の中で毎日部活の練習があり、休み時間に日焼け止めを塗っていたところ、先生から「学校に日焼け止めを持ってきたらいけない」と怒られたと。一方で学校の先生たちは、サングラスに長袖長ズボンで、完全防備。なぜ未来あるわたしたちの肌は守られないんでしょうか?という内容でした。その後、日本皮膚科学会や文部科学省、環境省などに取材をしたところ、国としては日焼け止めの使用を推奨しているにも関わらず、通知にタイムラグがあって、教育現場にまで下りてきていなかったことが明らかになったんです。この調査を終えて、「明日記事を出しますよ」とこの女の子に連絡をすると、「明日の朝刊がとても楽しみです」という嬉しい返信がきました。
若い方に関心を持ってもらうためには、まずは若い人たちにどのような悩みやニーズがあるかを知ろうとすること。そのために、若者が連絡しやすい窓口を設けることが、とても重要ではないかと思います。そこで、困っていることや知りたいことについて我々が話を聞かせてもらって、それに応えるような報道を作っていけば、信頼関係を紡いでいけるのではないでしょうか。
異業種連携で読者の困りごとに立ち向かう

―『あな特』を通じて読者の方と直接繋がっている一方で、企業の広報・PR担当者に求めたいことや要望などはございますか?
よく「こういうイベントや取り組みを取材してください」っていう依頼が来るんですけど、それは別の窓口があるので『あな特』では取り上げられません。しかし、時々企業からも「これはおかしくないか」「この企業のこれは問題ではないか」などといった調査依頼が来るので、その時は我々も喜んで取材するようにしています。『あな特』の問題提起を受けて企業が動くなど、消費者のサービス向上や、よりよい社会、みたいなところで一緒に連携して取り組みができればいいなと思っています。
企業にしても行政にしても、もっともっと繋がって、お互いとってウィンウィンな関係を築いていくことが必要ではないかと思います。情報のインプットの部分では読者と繋がって、アウトプットの部分では、異業種のように今まで連携していなかったところと組むことで、今まで情報を届けられなかったところに届けられるはずです。
クロスメディア戦略とブロック紙の可能性
“連携ジャーナリズム”で届けたい人に情報を届ける
―新聞社として、具体的にどのような連携を作ることが望ましいと思いますか?
ブロック紙には、「グローカルメディア」としての可能性があると思います。“グローバルに考えて、ローカルに行動する”という造語の通り、広域的な視点を持ちつつ、地域に根差した取材ができるのが、ブロック紙の強みです。またブロック紙には、地域に軸足を置きながらも全国規模の取材ができること、そして、ひとりの記者が体験できる仕事の幅が広いという魅力もあります。
このブロック紙ならではの強みを生かして、西日本新聞では『JODパートナーシップ』というものを立ち上げました。このパートナーシップでは、地方紙連携として①ノウハウの共有②コンテンツ(記事)の共有③ネタ/取材テーマの共有を行っています。

全国に広がる『JODパートナーシップ』のネットワーク
例えば以前、北海道新聞が「札幌市内のある店が『ラグビーW杯歓迎』という言葉を掲げたところ、『商標権に違反する』と指摘された」という調査依頼を受けて、「それっておかしくないですか?」という内容の記事を載せました。その記事に関して、同じくラグビーが盛んな岩手日報が記事化し、さらに両紙の記事を紹介しながら、西日本新聞が九州での事例を紹介。またさらにそれを受けて神戸新聞が記事を書き、青森の東興日報も記事を書いて…と、まさにラグビーのパス回しのように記事が日本中を転がっていって、より分厚い記事になったことがありました。一点だけ欠点があるとすれば、署名がどんどん長くなっていくことですかね(笑)
現在では、日本全国のローカルメディア23社27媒体にこのネットワークが拡がっています。これによって、日本中で手分けして取材し、記事を書ける仕組みが整ったことになります。困りごとをローカルメディアに相談できるというローカルインフラ網が出来上がったこと、地方紙連携ができるようになってきたことは、大きな成果だと感じています。記者の手が足りない中でも、全国の新聞社と連携してやっていける。これも『JODパートナーシップ』の魅力です。
新聞からネット、テレビ、ラジオへ
―横の連携を持つことで、取り上げられる情報の幅が広がるだけでなく、地域の外へ情報を届けることも可能になるんですね。
ただ、新聞だけではどうしても情報を届けきれないのも正直なところです。調査と取材を行うことは今までと何も変わらないんですけど、情報の集め方と、特に届け方の部分については、我々も工夫していかなければならないと思っています。
そこで最近、西日本新聞社には『クロスメディア報道部』という部署ができました。現在、フジテレビ系列の『テレビ西日本』と、テレビ東京系列の『TVQ』が、『あな特』のパートナーになっていて。『テレビ西日本』の方は、毎週土曜日の情報番組の中に『あな特』とのコラボコーナーがあり、一緒に連携して取材したり、報道を伝えたりしています。『TVQ』の方では、平日夕方のニュースの時間で「特捜Qチーム」という企画が始まりました。『あな特』に寄せられた情報をテレビ局にも共有して、テレビ局側が自分たちで取材して報道して、その報道内容を逆に我々新聞社が貰ったり、WEBでショート動画を流したり…っていうことを展開していく計画です。
あとは、ラジオ局『FM福岡』とも連携しています。毎週火曜日の夕方に『あな特』のコーナーがあって、そこでもDJの方からリスナーに対して情報提供を呼び掛けて、FAXやメールが来るようになっています。今後も上手く連携を形にしていけたらと思います。紙もWEBも波も、それぞれの特性を生かして、西日本新聞のファンを増やして信頼を高めようと取り組んでいるところです。
より良い社会を目指すグローカルメディアの挑戦

―読者からの相談内容によっては、調査するのにかなり体力がいるものもあると思いますが、ひとつの調査にかける時間であったり、そこの見切りというのはどのように行っているのですか?
『あな特』以外の記事と同じで、相談からすぐ記事になるものと、記事になるまで時間がかかるものがあります。中には、『あな特』スタート時から現在までずっと、2年半も取材が続いているものもあります。
『あな特』の一番の悩みは、次から次へと調査依頼が来て、そのすべてには応えきれていないところです。なので、西日本新聞の単独でやらずに、他社や他業種と連携して、人の手を借りることがカギだと思っています。場合によっては、読者の方にも力を借りることも必要ですし、喜んで協力して下さる読者の方々もいらっしゃるので、読者の方々と今まで以上に協働できる仕組みを考えているところです。
―さいごに、メディア業界や生活者に向けてメッセージをお願いします。
「新聞はオワコンだ」と思っている方も多いと思いますし、実際にオワコンと言われているのが現状です。しかし、私の新たな赴任先の中国では、新聞というのは”紙媒体”ではなくて、“ニュース”という意味です。「新聞紙社」ではなく「新聞社」の使命はこれからも変わらないと思っています。
ただ、そのためには我々も変わっていかなければなりません。ひとつは、読者と繋がること。もうひとつは、地域と繋がり、自分の地域だけではなくて全国と繋がる。さらに他媒体や異業種と繋がって、その先の世界と繋がること。このように、地域最強のメディア同士で繋がって、より良い社会を目指す「グローカルメディア」としての挑戦を続けていきたいですし、そういった意味で、我々の合言葉は「伸びしろしかない」だと思っています。まだやっていないことが多すぎるので、反対にまだまだやれることがあると確信しています。ぜひみなさんもあな特通信員にご登録いただれけば幸いです。

坂本 信博(さかもとのぶひろ)
マレーシアの邦字紙記者、商社勤務を経て1999年に西日本新聞社に入社。長崎総局や宗像支局、社会部、東京支社報道部、クロスメディア報道部などを経て、2020年8月から中国総局長(北京特派員)。主に医療や教育、安全保障、子どもの貧困、外国人労働者をめぐる問題などを取材し、調査報道に従事。
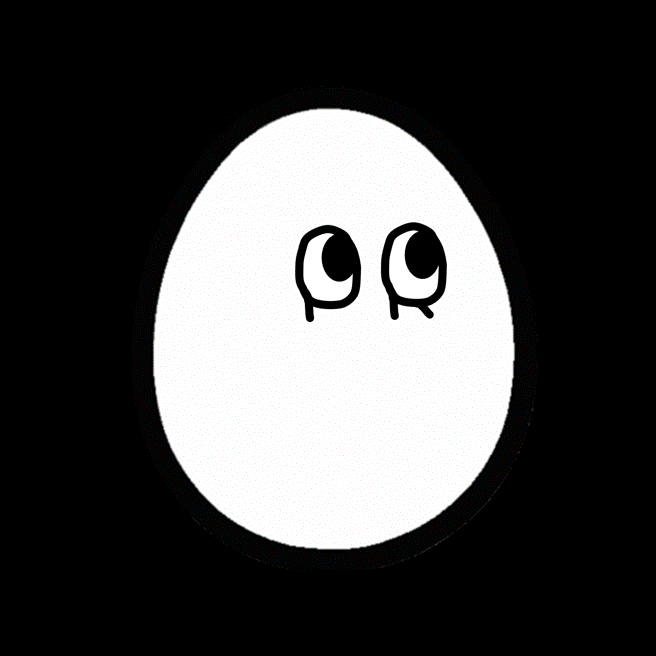
1995年生まれ大阪育ち。2018年同志社大学卒業後、株式会社マテリアルに新卒入社。1年目でウェブメディア『PR GENIC』を立ち上げ、記事の執筆と編集全般や、セミナーの企画など、コンテンツ作りを幅広く担当。半年間ハウスメーカーのマーケティング部への出向も経験。現在はオープンイノベーション支援に従事しつつ、外部アドバイザーとして編集のサポートを行っている。