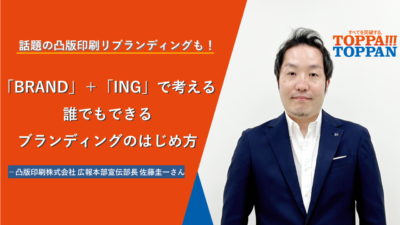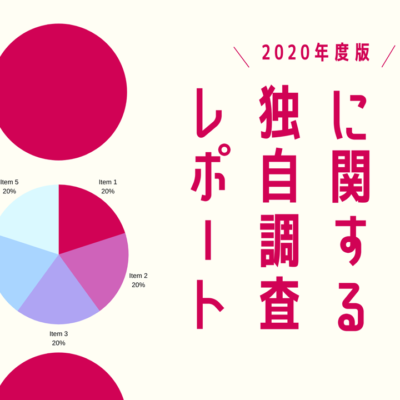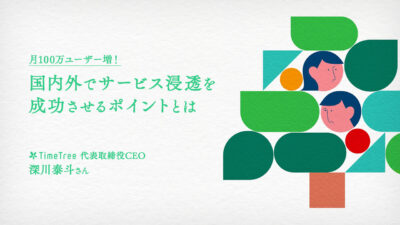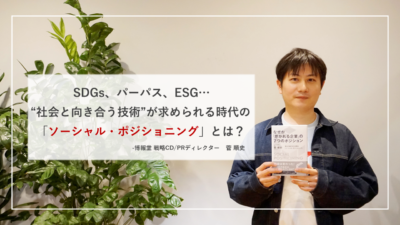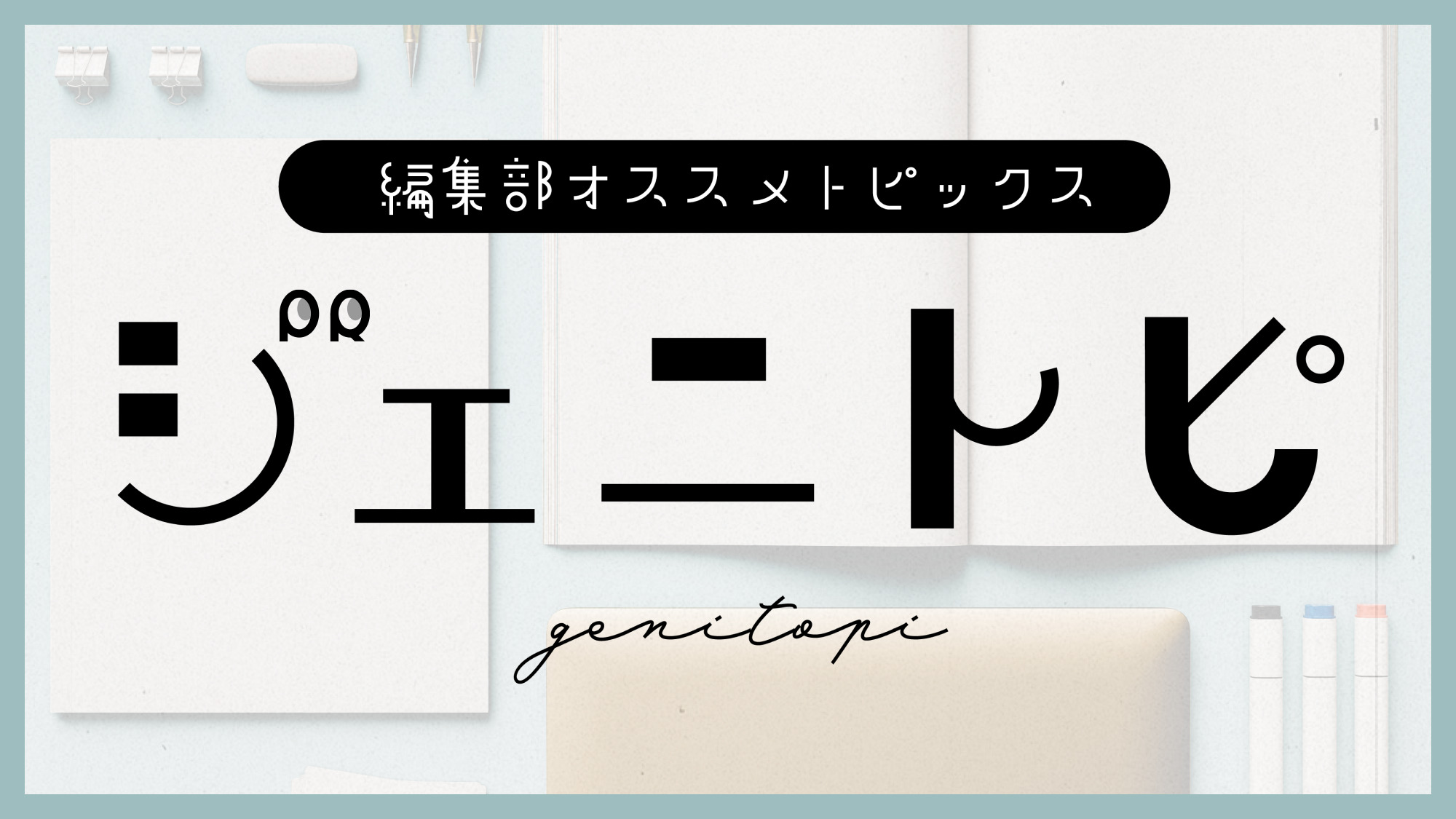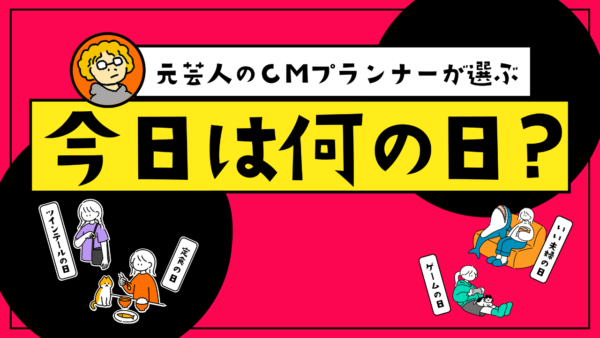日本の食卓には欠かせない調味料の一つである醤油。薄口、濃口、甘口といった味わいのみならず、近年はだし入りや無添加など、こだわりの調味料としての側面も持ち、多くのメーカーから多種多様な醤油が発売されています。
そんな醤油業界に、味以外のアプローチで新しい風を吹かせたのが『透明醤油』です。醤油の味はそのままに、素材の色を活かす透明醤油は、イタリアンやフレンチのシェフからの注目を集め、関連商品も次々と発売されるヒット商品となりました。テレビなどのマスメディアにも数多く取り上げられ、世界で反響を呼ぶこの人気商品を開発したのは、明治時代から醤油製造を営む株式会社フンドーダイです。
老舗企業である同社が、なぜ固定概念を覆した『透明醤油』を開発したのか。2019年の販売開始から、海外・インバウンドに注力したことで、国内でも再度注目を集めた背景とは。代表取締役社長の山村脩さんに伺いました。
| 株式会社フンドーダイ 代表取締役社長 山村 脩 東京都出身。慶應義塾大学法学部卒業後、1992年證券会社にて営業として活躍。ベンチャー企業を経て、食に関わるビジネスを志して熊本県に移住。2013年株式会社五葉フーズ(現フンドーダイ)常務取締役に就任。2014年五葉、五葉フーズ、フンドーダイの経営統合によりフンドーダイに参画、2018年より現職。創業150周年にあたり開発した新商品『透明醤油』をヒットさせる。 |
CONTENTS
“醤油は黒い”という固定概念を覆す、150年目の挑戦『透明醤油』

『透明醤油』シリーズ
ー『透明醤油』とはどのような商品なのでしょうか。
『透明醤油』とは、その名のとおり色が付いていない無色透明の醤油です。「透明醤油シリーズ」としては、『透明醤油』含め全4種類を展開しており、その他関連商品としてムースタイプの醤油やシートタイプの味噌・醤油、わさびオイルなども展開しています。
—商品開発の背景について教えてください。
弊社は1869年に創業した、醤油をはじめとする調味料や食品の製造会社です。会社が醤油の製造を開始して150年の節目を迎える2019年に、今までやったことのないチャレンジングな商品を開発しようと思ったことが『透明醤油』誕生のきっかけでした。試行錯誤のなかで、発酵過程で発生するアルコール成分を除去する「減圧濃縮法」を編み出すことに成功。これにより、たとえば、宗教等でアルコールが禁じられている国などにも進出できるようになることから、アルコールフリーは大きなアドバンテージになると考えたんです。そして、その技術を応用して色を無くすことができると分かり、さらに開発を進め、透明の維持に成功したのが『透明醤油』です。
32の国・地域で展開。海外展開成功の裏側
海外人気の火付け役は、現地の日本人シェフ

代表取締役社長 山村脩さん
—『透明醤油』は、32の国・地域で展開していると拝見しました。商品開発当初から、海外展開は視野に入れていたのでしょうか。
当初から海外市場は視野に入れていましたが、発売直後はコロナ禍真っ只中だったため、まずは国内の展示会を中心に出展していくことになりました。2021年から海外展示会に参加しはじめ、2022年時点ではアジアから欧州、北米を中心に愛用されています。
最初に出展したのは、2019年にドイツで開催された「食品・飲料関連見本市ANUGA 2019」。その際には、『透明醤油』でシャンパンタワーのようなグラスタワーを作るなど目を引く工夫もしましたが、想像以上に和食や醤油という文化が受け入れられていたため、とても好評でした。
—そこから、どのようにして海外人気に火がついたのでしょうか。
きっかけは、海外進出している日本人シェフでした。面白いのが、和食店ではなく洋食店やフレンチ、イタリアンの日本人シェフが興味を持ったことです。西欧料理だと、通常は料理にソースを使うのが一般的ですが、彼らは日本から持ち込んだ「だし」や「旨味」を料理に活用していました。「透明ならジュレに使える」「素材の色味を邪魔しない」と注目が集まったのです。
料理人やシェフは、料理のプロフェッショナルなので、開発者である私たちが思いもしないような使い方を、次々と生み出していました。ローカル料理の可能性を感じると同時に、プロはすごいと衝撃を受けましたね。
日本の価値観を押し付けないコミュニケーションが商品の可能性を広げる

フンドーダイが展開する調味料商品(一部)
—海外展開する際に意識したことはありますか。
日本人の価値観を押し付けないことですね。海外には、その土地に根ざした食文化やローカルフードがあります。日本ではあり得ないと思うような使い方やアレンジを、日本流に是正するのではなく、現地の食文化を尊重するようにしています。
—具体的にどのような使い方をされていたのでしょうか。
たとえばドイツでは、ソーセージの加工工程で醤油を使って旨味を出しています。私たちからすると、加工肉には調理後に味付けをするイメージですが、ドイツでは、製造する際の下ごしらえに醤油を活用することで、旨味が出せると考えるのです。
また、フランス・パリの和食レストランでは、天ぷらに『透明醤油』のスプレーをかけて提供しています。日本だと、天ぷらは天つゆにつける、もしくは塩をふりかけて食べますよね。しかし彼らは、「天ぷらから塩がパラパラ落ちてしまうから、味が付かない。皿も汚れて美しくない」と考え、均一に塩味が行きわたるようにスプレーを用いるんです。
個人的に印象に残っているのは、アラブ首長国連邦ドバイでの使い方です。そこでは、餃子に弊社の『トリュフ醤油』を付けて食べるのが美味しいと言われました。日本人だと、主張の強いニラとトリュフの組み合わせは、相性が悪いように思いますが、ドバイでは、2つの香りが混じり合うのがたまらないと好評だったんです。このように、日本人の価値観を押し付けないことで『透明醤油』の可能性がどんどん広がっていることを実感しています。

アンテナショップ『出町久屋』
—東京浅草のかっぱ橋エリアには、初のアンテナショップ『出町久屋』をオープンしています。直営店を開業した狙いは何ですか。
『出町久屋』は、海外での反響を受け、そのブリッジとして位置づけています。浅草は、平日でもインバウンド客が押し寄せる、言わずと知れた人気観光地。また、徒歩圏内にあるかっぱ橋道具街は、日本人はもちろん、各国の料理人やシェフが調理器具を求めて集まる、料理人のメッカです。弊社のアンテナショップとして、これ以上にない立地でした。2022年の開店以来、インバウンド客を中心に、多くのお客さまにご来店いただいています。
さらなるローカライズで『透明醤油』を世界に普及する

—海外展開を経て、国内での反響や評判に影響はありましたか。
結果的に、国内でもニーズは高まっています。『出町久屋』には、日本のお客さまも数多く来店されますし、パスタソースやサラダドレッシングなど、幅広く活用してもらっています。また、透明だと衣服についても汚れが目立たないため、揺れで機内食の調味料をこぼすケースがある、航空会社からお問い合わせをいただいたこともあります。私たちが思った以上に色々な広がりを見せてくれる商品となりました。
—今後、『透明醤油』としてどのようなことに挑戦していきたいと考えていますか。
今後は、刺身なら『透明醤油』、クラムチャウダーなら『透明醤油でつくっただし醤油』というように、メーカー発で商品の活用方法を広めていくことが目標です。現在は、商品の蓋についている「NFCタグ」をスマホで読み取ると、商品を活用したおすすめメニューのレシピが表示されるようにしています。レシピは、スマホに登録してある各国の言語に翻訳されるので、お客さまはスムーズに『透明醤油』シリーズを活用できる仕組みになっています。
ただ、海外視察を通して、私たちも想定していない使い方をされていることが分かってきたので、現在は、このレシピのバリュエーションを強化すべく、海外のレストランで『透明醤油』シリーズがどのように活用されているのか、より詳細に調査しているところです。
私たちは食品メーカーなので、企業主導で提供するプロダクトアウト型ではなく、市場のニーズを汲み取って開発するマーケットイン型の商品開発をおこなわなければなりません。そのためには、グルメトレンドはもちろん、国や地域ごとの味覚の好みを把握し、ローカルの食文化に合わせて商品を調合する必要があります。これからも、中小メーカーである私たちならではの方法で、『透明醤油』を広げていきたいです。

1984年生まれ、千葉県出身。アパレル会社の営業兼販売員、出版社の月刊誌編集、IT企業の広報・プロモーションを経て、編集・企画・ライターとして独立。現在はビジネスメディアを中心に活動している。経営層から学生まで、人物取材が得意。